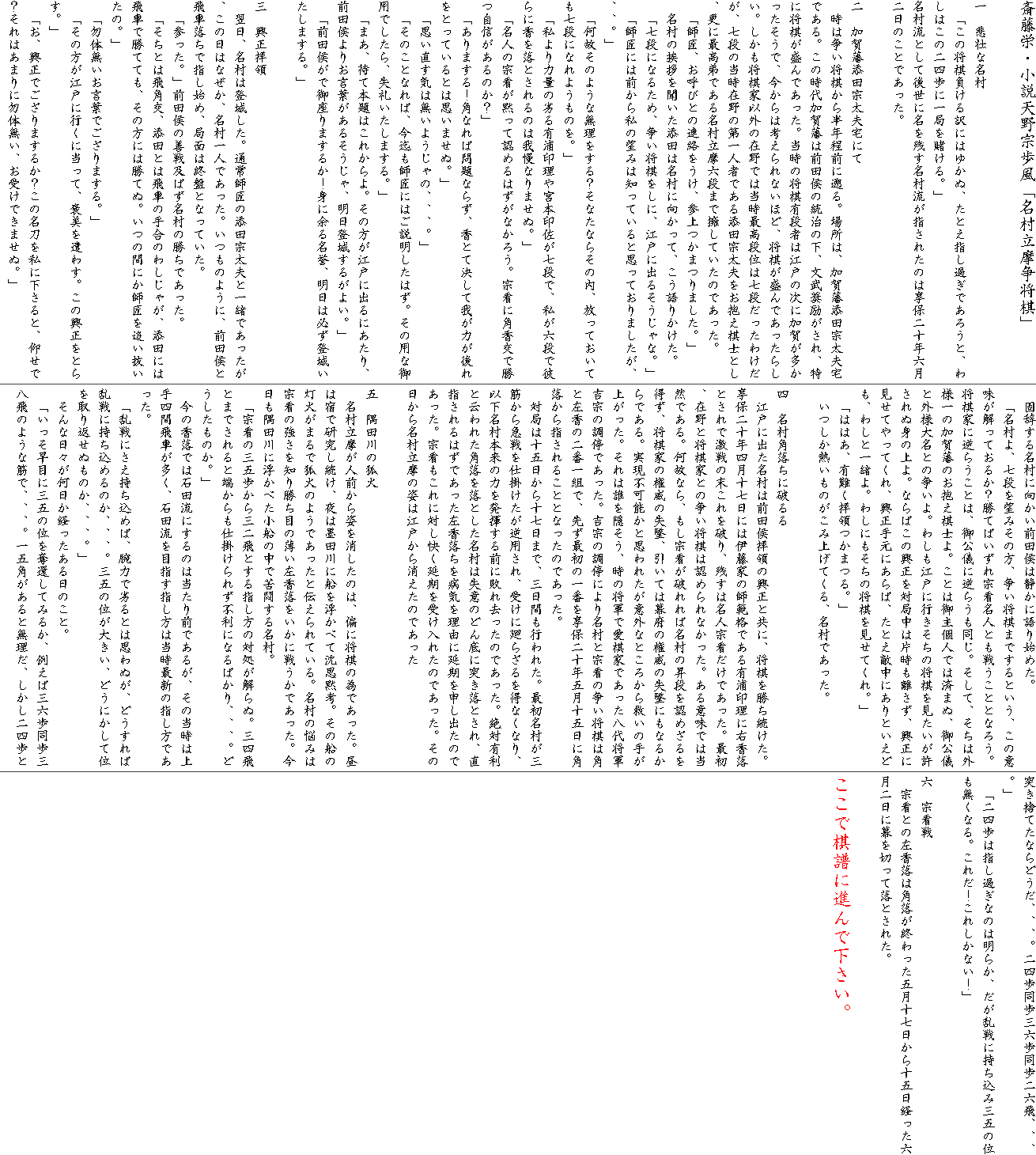
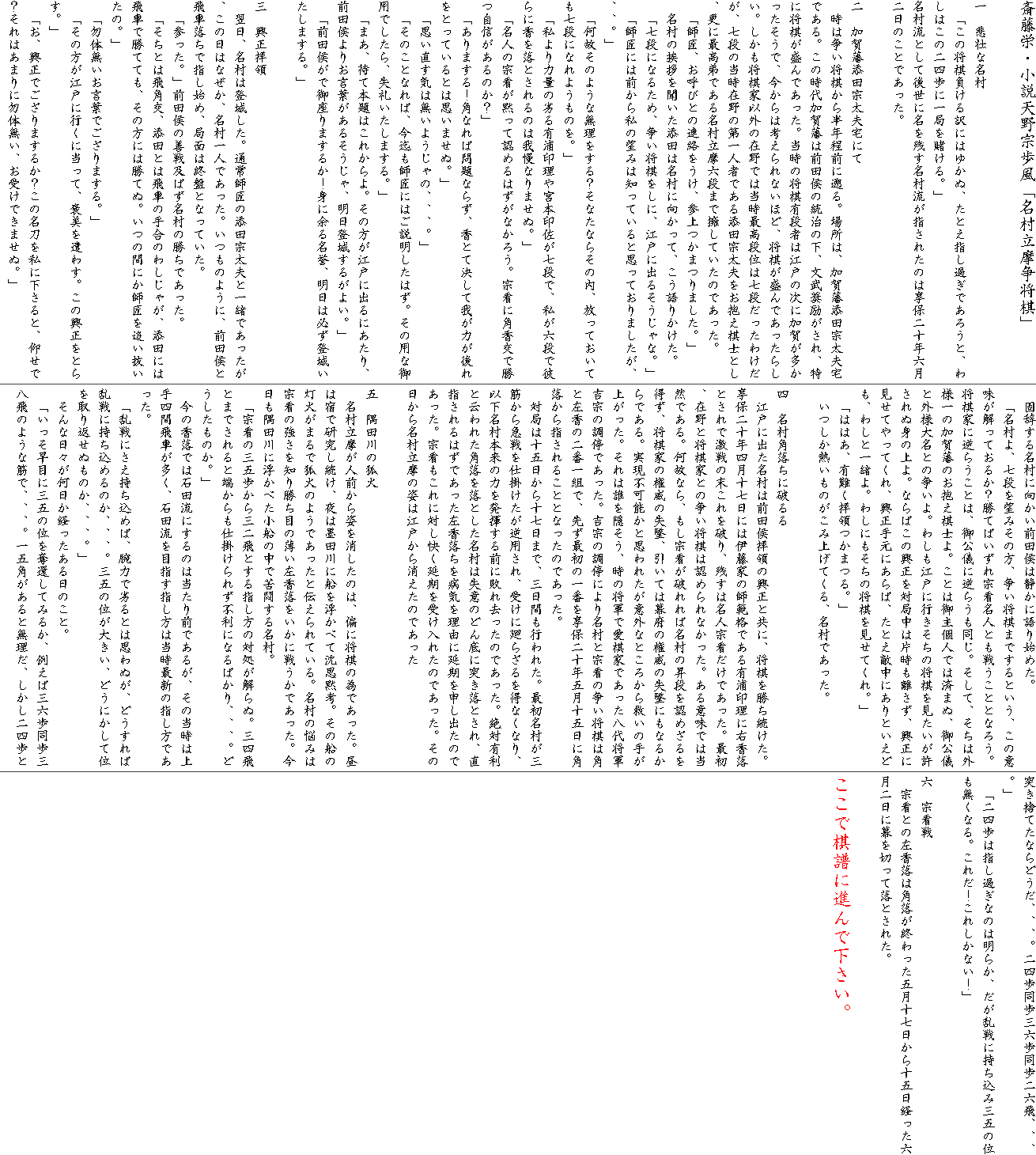
ここで棋譜にすすんで下さい。
ここで本編に戻って下さい。
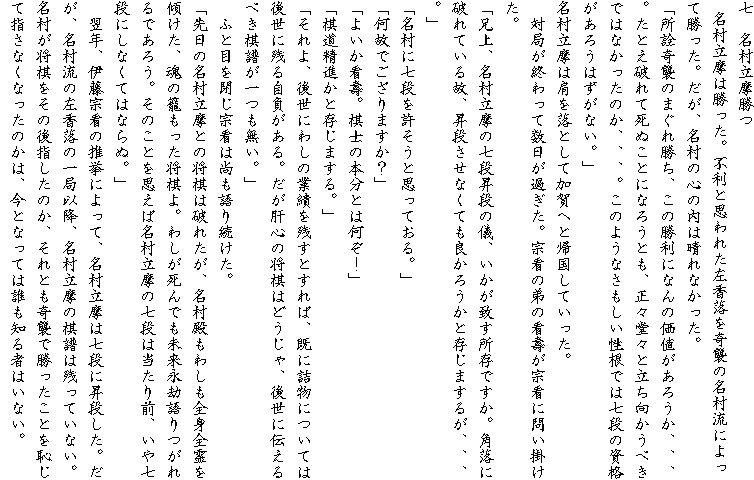
いかがでしたか?小説名村立摩は?なんか凄く長くなってしまい、自分ながらなんで此処迄と思ってしまいます。ただ途中から名村立摩に感情移入しちゃいました。ある意味では名村立摩に書かされたという感じでしょうか。
少し補足しますと、名村立摩は加賀出身で添田宗太夫の門人ということは解っていますが、あとの経歴はよく解りません。文中の宗看の詰物は「将棋無双」(別名詰むや詰まざるや)で弟看壽の「将棋図巧」と並んで二大傑作作品集として現在に伝わっています。
最後に名村立摩が本当に七段になったのかについては、本によって異なっていて、角落ちに負けたから六段のままだったという本と、香落ちに勝ったから七段になったと二つあり、どちらが正しいか解りません。